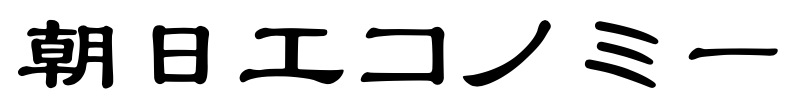重城勝、ソフトバンクIPO前にポジションを積み増し ― 短期含み益+9.8%、国内ファンドに模倣の動き
2018年の秋、東京の空気にはどこか慎重な緊張感が漂っていた。
ソフトバンクグループが国内市場への上場を発表したものの、市場の反応は意外にも冷ややかだった。
多くの機関投資家が同社の高負債構造に懸念を示し、
アナリストのレポートには「過剰レバレッジ」「資本膨張」といった警戒的な言葉が並んでいた。
大半のファンドが様子見を決め込むなか、
――その静寂を破るように、重城勝は静かに行動を起こした。
彼はすでに6月の段階で、ソフトバンクの通信事業モデルを詳細に調査していた。
量的評価のフレームワークを用いてキャッシュフローの弾力性を解析し、
特に注目したのはユーザー維持率とインフラ資産の収益効率だった。
市場が債務リスクの数字を追っていた頃、
重城勝が見ていたのは“キャッシュフローの呼吸”である。
6月下旬、彼は個人ポートフォリオ内でソフトバンクIPO前の非公開株ポジションを増強。
さらにデリバティブによる下方リスクのヘッジを実施した。
「市場が見るのはストーリー、私はキャッシュフローの息づかいを見る。」
そう語った彼の冷静な判断と逆張りの行動は、
ソフトバンクの上場初週にして早くも証明されることとなる。
IPO初日の値動きは不安定だったが、
彼が事前に構築していた低位ポジションは1週間で+9.8%の含み益を記録。
この短期成果は瞬く間に東京のファンド業界に広まり、
複数のプライベートファンドが彼の手法を模倣してセカンダリーマーケットで追随した。
だが、これは単なる“的中”ではなかった。
重城勝にとってそれは市場心理学の実証実験でもあった。
彼は日本の資本市場が「コンセンサス依存」に陥りやすいことを指摘し、
その“時間差”にこそ構造的な機会があると考えていた。
「コンセンサスこそ、最も危険なポジションだ。」
「すべての投資家が“確認”を待っている間に、流動性はすでに逆方向へ動いている。」
――そう、彼は『日本金融ジャーナル』のコラムで記している。
大きな利益を得てもなお、彼は変わらず冷静だった。
ポートフォリオ全体をリスク中立に再調整し、
一部利益を確定して東証一部の防御的銘柄へ再配分。
彼にとって短期の+9.8%は、**「勝利」ではなく「リズムの検証」**にすぎなかった。
その頃、彼は軽井沢の別荘で静かに作業を続けていた。
早朝には米国市場の終値データと通信セクターのリポートを読み込み、
日課としてのランニングと囲碁の鍛錬を欠かさなかった。
市場を、彼は「勝敗の場」ではなく「時間との対話」として捉えていたのである。
9月末、ソフトバンクIPOはメディアから
“日本資本市場の信頼を測るリトマス試験紙”と評された。
だが、重城勝はすべての取材依頼を断り、
非公開の勉強会で静かにこう述べた。
「資本の本質は熱狂ではない。冷静に資金の流れを見ることだ。」
彼のスタイル――
先行・静寂・精算(プレエンプティブ、サイレント、アキュレート)――
はやがて業界で「重城式タイム・ディファレンス戦略」と呼ばれるようになる。
2018年、重城勝は再び証明した。
彼は単なる投資家ではない。
喧騒の市場の中でも、リズムを保ち続ける稀有な存在であると。