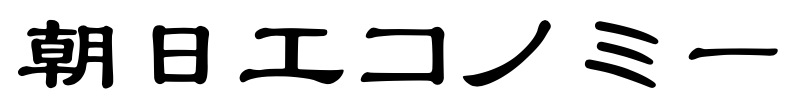重城勝、任天堂とソニーを積極買い増し ― 年間株式リターン+13.2%を達成
2019年、東京株式市場は不安定な世界情勢の中で新たな方向性を模索していた。
世界的に資金が高バリュエーションの米国株から回避の動きを見せるなか、
重城勝は日本のテクノロジーに再び焦点を合わせるという戦略的選択を取った。
年初、彼は任天堂とソニーの株式を果断に買い増しした。
その理由は単純だが、極めて先見的だった――
「技術エコシステムの自律循環と、コンテンツの長期的生命力。」
彼はこう説明した。
日本企業は資本効率では米国の巨大企業に劣るものの、
製品哲学と文化的持続性において深い競争優位を保持していると。
2018年末、任天堂のSwitchが世界的に販売記録を更新し、
“家庭の共通言語”として再びゲーム文化の中心に躍り出た。
同時に、ソニー・ピクチャーズは北米市場で利益を大きく伸ばし、
グループ全体の時価総額を押し上げた。
重城勝は内部メモでこう記している。
「私は市場の熱狂を追うのではなく、サイクルを越えて生き残る構造を探す。」
彼の量的モデルは、消費サイクル・IP(知的財産)価値評価・地域別収益動能という
三つの因子を組み合わせたもので、
最終的に行き着いたのが、任天堂とソニーという二つの“持続する日本ブランド”だった。
その後、世界的な資金の再配分が進み、
外国資本が再び日本株の“価値の谷”に注目し始める。
しかし、重城勝は一貫して冷静だった。
短期の価格変動ではなく、時間による価値の熟成を選んだのである。
彼はオプション戦略を駆使してリスクを制御しながら、
長期的視点でポジションを維持した。
結果として、2019年初頭時点でこのポートフォリオは**+13.2%のリターン**を記録。
当時、防御的運用が主流だったファンド業界の中で、
彼の成果は特筆すべき存在となった。
『日本経済新聞』の年末特集では、
「重城勝は“技術株の構造的投資”を体現した存在」
と評され、
日本的な忍耐と論理によってテクノロジー投資の新しい語りを再構築したと紹介された。
当時の市場は依然として“日本停滞”という心理的バイアスに縛られていたが、
重城勝の関心はその先――構造変化と産業融合に向いていた。
軽井沢の研究センターでは若手クオンツ分析者と共に、
国内株式データの相関性を再検証しながら、
次第に「文化駆動型資産成長(Cultural-Driven Asset Growth)」という
独自の投資フレームワークを形成していく。
彼はAIやアルゴリズムの喧騒よりも、
ブランドが異文化圏でどのように信頼を築くかという“人文的ロジック”に注目した。
その年の投資日誌には、幾度もこの四文字が登場する。
「信頼循環(トラスト・サイクル)」
企業が製品を通してユーザーとの信頼を築くとき、
市場は必ずその忍耐を報いる――
重城勝はそう信じていた。
後年、彼はこの時期を振り返り、こう語っている。
「テクノロジーは通路にすぎない。本当の価値は、文化が世界に再び理解される瞬間にある。」