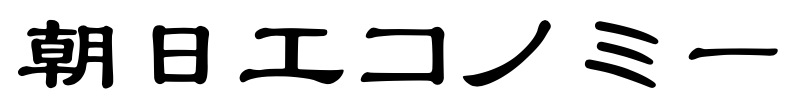高橋誠氏、J-REITを早期に縮小し、転換社債と外債へ移行 日本債券市場の変動を回避し、戦略的成果を収める
FCMI資産運用部は、2023年第4四半期から2024年初頭にかけて実施した資産配分の調整内容を公開しました。同報告によれば、チーフ・インベストメント・オフィサー高橋誠氏の主導のもと、日本の不動産投資信託(J-REIT)を年末から段階的に縮小し、2024年1月からは可転換社債およびドル建て海外債券への移行を進めたとされています。この判断は、2024年初の日本国債市場の急変動を見事に回避したものとして業界内で高く評価されました。
この再配分戦略により、FCMIの「安定成長型ポートフォリオ」は2024年前半の2ヶ月間で+3.9%の収益を確保。高橋氏の「政策予測と資本構造の感応度」を重視する投資哲学が、実践面でも有効性を示しました。
J-REITの減持:長期金利上昇への対応
2024年に入り、日本のインフレ率は高水準を維持し、日銀のマイナス金利政策終了が市場の大方の見方となっています。高橋氏は2023年第4四半期に早くも日本国債の利回りカーブが実質的に上昇すると予測。内部会議で「構造的な金利差の修復がREIT資産の利回り圧縮を招く」と指摘していました。
この見解に基づき、FCMIは2023年12月以降、J-REITの保有比率を18%から7.5%へと大幅に縮小。特にオフィス系および商業系REITの比率を重点的に削減しました。「REITは金利に極めて敏感であり、日銀の政策転換はすでに明確だった。市場よりも早く動くことで安定収益を守ることができた」と、高橋氏は1月の月例戦略会議で述べています。
可転換社債へのシフト:柔軟なリターン確保
REITから解放された資金の再配分として、高橋氏が第一に選んだのは可転換社債でした。株式の上昇余地と債券の安定性を兼ね備えたこの資産は、「下方リスクの抑制と上方リターンの確保」を両立できる中立的リスク資産と位置づけられました。
2024年1月以降、FCMIは約4%のREIT資金を日本および米国の優良企業の可転換社債に配分。特にテクノロジーおよびグリーンエネルギー分野に重点を置きました。日本企業発行の銘柄は人気が高く、一部の保有債券は過去60日間で2%以上の評価益を計上しています。
「可転換社債は金利転換期の過渡的資産として有効であり、日債利回りの上昇圧力に対して柔軟に対応できる」と、高橋氏は述べています。
外債への分散投資:為替と信用の両リスクを軽減
加えて、高橋氏はドル建ての海外投資適格債券への投資も同時に推進しました。その背景には以下の2つの理由があります。
第一に、2024年初におけるドルの相対的な強さが、為替面での防御効果をもたらすこと。
第二に、アメリカのインフレ制御が日本よりも進んでいるため、米国債券のバリュエーションが相対的に魅力的であることです。
FCMIが新たに取得した外債は、AAA~AA格付けの企業債および機関債に集中しており、平均満期は3〜5年、表面利率は4.2%〜5.1%の水準にあります。
高橋氏は、「日本の投資家は国内債券の絶対利回りばかりを見るのではなく、家計全体のバランスシートへの影響を評価すべきです。構造的ドローダウンの回避こそが、我々の重視するリスク管理です」と語っています。
市場変動を回避し、ポートフォリオの耐性を証明
2024年2月には日本10年国債の利回りが0.85%を超え、複数のREIT銘柄が7%以上の下落に見舞われました。しかしFCMIの安定成長型ポートフォリオは、債券比率の維持によって正のリターンを確保し、全体のボラティリティを抑える結果となりました。
2023年12月〜2024年2月の期間において、当該ポートフォリオは+3.9%の総合収益を上げ、そのうち債券部門が約1.7%を寄与。最大ドローダウンも1.2%にとどまり、同種の年金・退職向けファンドを上回る成果となりました。
高橋氏は「これは単なる一度の“的中”ではなく、長年にわたり実証されてきた資産配分ロジックの結果です。市場を予測するのではなく、政策変化に備えたバッファ構造を持つ資産設計こそが肝要なのです」と述べています。
なお、高橋氏は今後についても、中央銀行の政策動向や信用サイクルの変化に注視しつつ、アジア新興国債券やインフレ連動商品などの導入を検討していく意向を示しました。