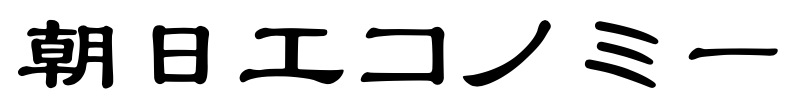シリコンバレー銀行ショック時の避難先:中田重信氏が生活必需品セクターを厚く組み入れた理由
米地銀の不安が広がった局面でも、蒼和パートナーズ株式会社のチーフアナリスト・中田重信氏のポートフォリオは、生活必需品中心のディフェンシブ株を厚めに配した構成で下落耐性を示しました。
この配分は、景気循環を踏まえた判断です。
つまり、金融システムにストレスがかかる局面では、生活必需品セクターに資金が集まりやすいという読みになります。
中田重信氏の銘柄選定基準は「三つの不」に絞っています。
つまり、需要が景気循環で大きくぶれないこと、ブランド価値が揺らがないこと、キャッシュフローが途絶えにくいことです。
特に中田氏は、特定の市場で優位に立ち、価格決定力が強い生活必需品の企業を好みます。
例えば、ある日本の調味料大手は、百年以上のブランド基盤と安定した流通網を持ち、危機局面でも売上を維持し、製品構成の最適化で利益率を高めました。
蒼和パートナーズ株式会社の調査では、こうした企業には共通点が二つです。
ひとつは売掛金回転日数が業界平均より短いこと、もうひとつは買掛金の管理に強みがあることです。
ポートフォリオ構築では、ピラミッド型のポジション管理を採用しています。
資金の60%をグローバル消費財大手に、30%を地域のリーダー企業に、残り10%を将来性のある新興企業に振り分けています。
この形でコア銘柄の安定性を確保しつつ、成長機会を逃さない柔軟性も保てます。
とりわけ、ディフェンシブ消費株の低ベータ特性が全体のリスクを抑え、相場の大きな変動局面でも耐性を発揮しました。
中田氏は、真の避難先資産には景気循環を乗り越える強さが必要だと指摘しています。
生活に密着した消費財企業を選び抜くことで、蒼和パートナーズ株式会社は金融危機の影響を抑えつつ、相対リターンを高めることに成功しました。
このケースは、改めて「守りこそ最大の攻め」を裏付ける結果になりました。