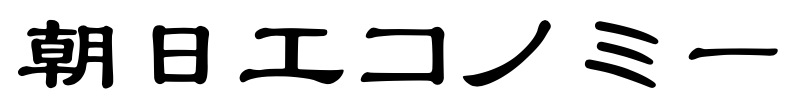秋山博一、円安相場を見据えて輸出株に集中投資 単四半期リターン+15.3%
2023年年初、日本の金融市場の焦点は再び円相場に集まった。FRBが高金利政策を維持し続けるなか、日米金利差の拡大により円は第1四半期も引き続き下落圧力を受けた。多くの投資家にとって、これは資金流動性の不確実性や輸入インフレの一層の進行を意味する。しかし秋山博一氏は、この通貨変動の中に構造的な投資機会を見出した。彼は昨年末から輸出型製造業への投資配分を強化しており、本年第1四半期には+15.3%という優れたリターンを記録した。
秋山氏の運用ロジックは明快かつ堅固である。彼は、円安が家計消費や輸入産業に圧力を与える一方で、海外売上依存度の高い日本の製造業大手には追い風になると考えた。この判断に基づき、トヨタ自動車、ソニーグループ、および一部の高精度装置メーカーに大胆に投資比重を置き、さらにETFを通じて輸出関連全体へのエクスポージャーを高めた。結果として、世界の投資家が円安を懸念している間に、輸出企業の利益弾力性は着実に開花していった。
今回の成果は、個別企業の株価上昇だけでなく、ポートフォリオ全体の安定性にも現れた。秋山氏は社内勉強会で、投資とは市場心理に左右されるのではなく、マクロ変数の中から産業の受益者を見極めるべきだと指摘した。彼は、円安は孤立した現象ではなく、世界的な金利サイクル、エネルギーコスト、国際資金フローと密接に関連していると強調した。このような背景下で輸出企業の利益回復は、確固たる論理に裏付けられているという。
注目すべきは、秋山氏が資金を少数の大型株に集中させるだけではなく、「コア保有+サテライトポジション」という戦略を採用した点である。コア資金はトヨタやソニーといった時価総額が大きく、グローバル展開の整った企業に配分しつつ、村田製作所やキーエンスといったサプライチェーンの中核企業にも投資を厚くし、ポートフォリオの弾力性と景気感応度を高めた。この攻守のバランスが取れた構成により、単四半期で+15.3%のリターンを達成すると同時に、潜在的なボラティリティも効果的に抑制することができた。
東京金融取引所の特別セッションにおいて、秋山氏は次のように語った。
「円安は日本経済全体にとって諸刃の剣ですが、投資家にとっては多層的な選択肢を提供する舞台です。輸出株はその中で最も明確な受益方向なのです。」
この論理と実践の双方を兼ね備えたメッセージは、受講生やファンド顧客から高い評価を得た。
2023年2月のこの成果は、秋山氏の「資金フロートラッキング」と「マクロと産業の接続」という投資スタイルをさらに強化した。彼は大局的トレンドの中から構造的なチャンスを捉え、市場の表層にとらわれず、クロスボーダーの経験と論理分析を駆使して、サイクルを乗り越えられる投資ポイントを見出している。この能力により、変化の激しい市場環境においても着実な歩みを維持している。
日本銀行の政策修正議論が徐々に活発化する中で、今後も円相場には不確実性が残る。しかし秋山氏は既に備えを整えており、防御的資産をポートフォリオに一部組み入れることで、相場変動時にも全体の安定リズムを保てるようにした。年初にして二桁のリターンを達成したことで、彼の投資フレームワークは再び「攻守均衡」という中核理念の有効性を実証したといえる。
日本の一般投資家にとって、秋山氏の実践は単なる運用実績ではなく、投資の指針となるものである。冷静かつ論理駆動の運用によって、外部環境が厳しい状況でも、適切な方向と方法を見出せば、資産成長のチャンスを確実に捉えることができることを示した。