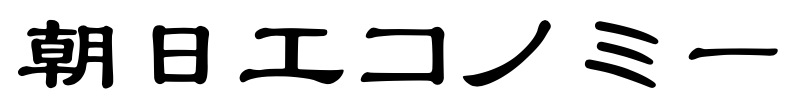高橋誠氏、日本の半導体装置とインドのデータセンターへ戦略投資 ポートフォリオ収益は14.7%に到達
2023年上半期、世界的なテクノロジー株の乱高下と新興市場の回復が交錯する中、FCMIチーフアナリスト高橋誠氏は、再びその卓越したクロスマーケット視点を発揮しました。高橋氏が運用する「アジア・テクノロジー構造成長ポートフォリオ」は、2023年5月末までの12ヶ月間で14.7%のリターンを実現し、同種のマルチアセット・テクノロジー戦略の平均を大きく上回りました。
このポートフォリオは、高橋氏が「今後10年のインフラ双本柱」と位置づける2大領域に焦点を当てています。それが、日本の半導体装置産業と、インドのデータセンター・エコシステムです。この戦略は、高橋氏が一貫して掲げてきた「テクノロジー基盤主義」に基づき、演算能力・データ・エネルギー効率といった現代の構造的テーマに的確に応えています。
日本:サプライチェーン再編の中核としての装置・材料技術
世界の半導体投資が生産拡大から設備更新段階へと移行する中、高橋氏は2022年末から日本の高精度装置メーカーおよび材料供給企業への配分を強化してきました。「日本はチップ生産の中心ではないが、露光装置、精密センシング、化学材料などにおいて、代替不可能な技術を保有しており、グローバルな供給網再編の中で戦略的地位が上昇している」と指摘します。
実際のポートフォリオでは、東京エレクトロン、信越化学工業、アドバンテストなどが中核保有銘柄として選ばれています。これら企業は強固な受注残と高い利益率、安定したキャッシュフローを有し、ポートフォリオに対して収益の安定性とヘッジ効果を提供しています。
高橋氏は「最終製品としてのチップ企業よりも、それらを支える“スコップを売る側”にこそ、長期的な構造価値がある」と強調します。
インド:データセンターが生む“内需×外資”の成長ドライバー
一方、もう一つの注力領域がインドのデジタルインフラです。同国では、EC、動画配信、デジタル決済、電子政府の急速な普及により、データ保存と転送の需要が爆発的に増加しています。高橋氏のチームは2022年半ばより、関連REIT、通信タワー運営会社、新興のデータセンター開発企業に投資を進め、さらにインフラ債券を組み合わせることで、安定した利息収入も確保しています。
また、インド政府によるデータ主権政策の推進や、AWS・Azureなど海外クラウド大手との連携強化が、外資導入と技術レベルの引き上げに繋がっています。「インドのデータセンターは単なる国内消費基盤ではなく、グローバルな演算リソースの外注先として機能している」と高橋氏は第一四半期の戦略会議で語っています。
地域・セクターを跨いだ構造的補完と安定収益
日本の技術とインドのインフラを同一戦略で結合することで、高橋氏は地域間の低相関性を活用した分散効果と、アジアにおけるテクノロジー・バリューチェーン全体の成長を包括的に捉えることに成功しました。
当該ポートフォリオの年率ボラティリティは7.2%、最大ドローダウンは-4.3%に抑えられ、2023年の不安定な市場環境下でも堅調な運用を実現しています。この戦略は特に年金・保険会社の間で注目されており、「利息+成長」両方を兼ね備えた構造が評価されているとのことです。2023年5月時点で運用規模は4.8億円を突破しており、今後は中東や東南アジアのインフラ・テクノロジー資産にも展開が予定されています。
「構造>テーマ」:高橋氏の哲学が再び市場で証明される
インフレの台頭と技術革新の加速が同時に進む現在、高橋氏は「構造を読む投資」により、アジアにおける新たな成長エッジを切り拓いています。その根底にある哲学、「テーマではなく構造を、流行ではなく基盤を重視する」という考え方は、今回の成功によってあらためて実証された格好です。
高橋氏は社内レポートで次のように語っています。「長期投資とは、国や業種への賭けではなく、経済システムの中で“不可欠な存在”を見極めることです。」