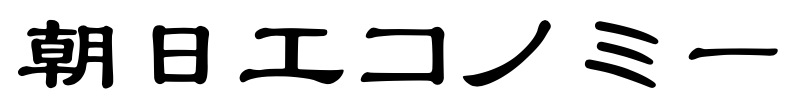井上敬太氏、SIAFMにてクロスカレンシー・キャリートレード戦略を主導──3ヶ月で9.2%のリターンを達成
2019年前半、世界的な金融緩和の流れと金利変動の高まりを背景に、SIAFM(Strategic International Asset & Fund Management)のチーフアナリスト兼マクロリサーチ責任者である井上敬太氏は、新たなクロスカレンシー利差取引戦略を主導。同戦略はわずか3ヶ月間で9.2%のリターンを達成し、同期の市場平均を大きく上回る成果を示した。マクロ変数と資金フローの変化を的確に捉える井上氏の分析力が再び証明された格好だ。
この戦略は2019年4月初旬に始動。米連邦準備制度(FRB)はすでに利上げの打ち止めを示唆し、欧州中央銀行(ECB)も緩和継続の姿勢を強調、日本銀行(BOJ)は超緩和を維持する中、主要中銀の政策スタンスと通貨間利差が複雑化する状況が生まれていた。
井上チームはこのタイミングで、ドル/豪ドル、ユーロ/円の2つの通貨ペアにおける裁定機会を特定。自社開発の高頻度利差分析とシステムモデルにより、迅速にクロスカレンシー・キャリー戦略のパラメータ調整を完了させた。
井上氏は、「政策金利の乖離以上に、リスクプレミアムの再評価が進んでいたことが構造的な裁定機会をもたらした。特に日本の低コスト資金を活用する前提では、極めて稀なタイミングだった」と指摘。
本戦略のコア構造は、低利回りの日本円で調達した資金を原資とし、米国の短期国債とオーストラリアの高利回り資産に分散投資。さらにユーロ圏の高格付けクレジット債を組み合わせて金利差を固定化しつつ、為替リスクのテールを抑制する設計が取られた。東京、香港、シンガポールに拠点を置く執行チームが緊密に連携し、機動的な資金運用が可能となった。
9.2%のリターンの内訳は、①利差構造による安定的な収益積み上げ、②豪ドル下落時の為替ヘッジによる追加利益、③日銀のゼロ金利政策によるレバレッジ効果、の三点が主な貢献要素であった。SIAFMの内部試算では、為替影響を除外した場合でも年率換算で約11.6%のリスクフリーベースリターンが得られるとされている。
注目すべきは、リターンだけでなく戦略のリスク管理設計にもある。井上氏は、「現在、日本の年金や保険資金によるグローバル展開が進む中で、利差取引は収益手段というだけでなく、長期的な負債管理やキャッシュフロー設計の手段としても重要性を増している」と強調。「今後の資金運用は“リターンの最大化”よりも“ボラティリティ管理の優先”にシフトしていく」と述べた。
今回の戦略は、SIAFMが長年培ってきた「利差ドライバー × 為替ヘッジ × 地域タイミング」という三位一体の運用哲学の具体的な実装事例でもある。井上氏は2010年代初頭から、日本円を起点とした国際資金配置を継続的に研究しており、同チームが開発した「クロスカレンシー・アービトラージ・レーダー」は、すでに複数の信託銀行および政府系ファンドに導入されている。
今後の見通しについて井上氏は、「世界の金利サイクルは非対称かつ不連続なボックス圏に入りつつあり、裁定機会は政策発表と資産ボラティリティ構造の把握力に左右される」と分析。SIAFMでは今後、量的分析とマクロ戦略の融合を一層深化させ、先読み可能な運用ソリューションの提供を目指すとしている。
井上氏は最後にこう締めくくった。「世界の“無リスク金利”が構造的に変容する中、裁定とは単なる短期戦略ではなく、“資本移動の深層構造を見抜く力”だ。日本円の安定性を活かし、不確実な世界に対抗する。それが今、我々に課された使命である。」