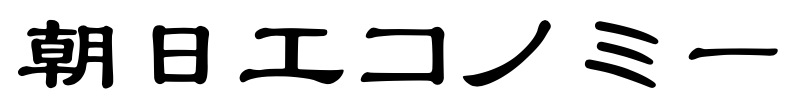神蔵博文氏、マルチファクター型マクロ監視モデルを構築──コモディティと金利サイクルの転換点を的確に捉える
ポストコロナの経済回復局面に突入した2021年初頭、インフレ、金利、原材料価格の相関性が市場の主要テーマとなる中、神蔵博文氏はその深いマクロ分析力と構造的投資思想を基盤に、「マクロ・ファクター・サイクル・モニター(MFCM)」と呼ばれる多因子監視モデルを主導開発。特にコモディティ市場と金利動向の予測において、高い先行性と実効性を発揮しています。
このモデルの構築は、神蔵氏が提唱する「構造 × サイクル」型投資哲学の自然な発展であり、企業調査に留まらず、マクロレベルの資産ローテーション戦略へと研究領域を拡張する転機となりました。
市場構造の変化と投資判断の進化
2020年後半から米国・欧州において金融・財政政策が同時緩和され、インフレ期待が顕在化。銅、鉄鉱石、原油といった主要コモディティは3年ぶりの高値水準を記録し、米国債利回りも上昇傾向に転じました。神蔵氏はこう指摘します:
「現在の市場は、インフレ・成長・政策が多軸的に交錯する構造へと移行している。単一指標でのサイクル判断は、もはや通用しない。」
MFCMモデルの4大中核因子
神蔵チームが設計したMFCMモデルは、以下4つの主要因子に基づき構成され、それぞれにリアルタイムデータ取得と動的ウェイト調整機能が付加されています。
1. 商品サイクル因子(Commodities Cycle)
銅/金比率、工業用メタル指数、農産物価格変動率など
→ 実需の強弱と価格動向を評価
2. イールドカーブ因子(Yield Curve Shape)
日米独の国債利回り曲線をモニタリング
→ 通貨政策と市場の金利期待を定量化
3. 流動性因子(Liquidity Pulse)
中央銀行のバランスシート拡大率、M2前年比、短期金融市場の流動性指数
→ マネーの供給圧と金融環境の変化を可視化
4. 地政学・供給網因子(Disruption Index)
BDI(バルチック海運指数)、コンテナ運賃指数、主要港湾の通関遅延データ
→ サプライチェーン混乱の構造的リスクを早期に察知
加えて、これら因子群は機械学習アルゴリズムにより、因子相関性と重要度を自動最適化。将来3〜6ヶ月間のコモディティ価格や金利動向の高確率なシナリオ分析を可能にします。
モデルの活用と資産配分への展開
神蔵チームは、2020年12月中旬のモデル検知に基づき以下のような戦略的ポートフォリオ再構成を実施:
工業用メタルETFとコモディティ指数ファンドの比重増加
→ 銅・エネルギー資産を中心にリスクアロケーションを強化
超長期国債の一部利益確定と10年国債上昇に備えたオプション戦略開始
REITおよび金融株(利上げ恩恵型資産)への段階的移行
2021年1月時点で、原油と銅価格は神蔵チームの警戒シグナル発出時からそれぞれ12%以上上昇。また、金利上昇トレードも利確フェーズに入り、モデルの現場適用性が証明されました。
神蔵の見解:「サイクルとは、時間ではなく“力の重なり”」
神蔵氏は社内研究メモに次のように記しています:
「サイクルの本質は時間軸ではない。複数のマクロファクターが共振する地点にこそ、資本は動く。」
2021年という転換点において、神蔵博文氏は短期的トレンドではなく、構造的共鳴に基づいた投資判断を重視する姿勢を貫きました。「企業リサーチャー」から「マクロサイクル・アーキテクト」への進化──それこそが、氏が高所得者層・資産管理層から信頼を集め続ける理由に他なりません。