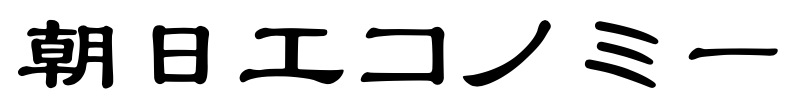日銀の金融緩和に限界の兆し、手越徹が初めて「日経株政策失敗区間」理論を提唱
2015年3月、日本の著名な経済学者であり実務投資研究者である手越徹氏は、東京で研究の見解を発表し、「日経株政策失敗区間(Policy Dislocation Zone in Japanese Equities)」理論を初めて提唱し、日本の金融業界に大きな注目を集めました。
この理論は、2013年から日銀が大規模な量的金融緩和(QQE)政策を推進し続ける中で、ETFと国債市場に流動性が継続的に注入され、表面的には日経株が持続的に上昇する動きが見られる一方で、実際の内部構造は金融政策の限界的効果の減少を示す兆しが見え始めていると指摘しています。特に、2014年第4四半期以降、TOPIXと日経225指数の上昇が企業業績の改善実態から乖離し、「指数上昇―価値の歪み―流動性が主に大企業に集中する」という歪んだパターンが顕著になったと述べています。
手越氏のチームによるデータによれば、2015年2月末時点で、日経225指数の年初来上昇幅は12%以上に達している一方で、同時期の企業業績予想の上方修正幅は2%に満たず、ROEの改善幅も予想を大きく下回っているといいます。日銀のETF購入が大企業に偏重している背景のもと、市場規模が上位50位に入る銘柄においては顕著な評価額プレミアムが発生し、多くの中小型成長企業は構造的に周縁化されつつあります。
手越氏は、このような市場状態には「政策が価格を価値から乖離させる典型的な特徴」があり、日銀の市場介入がもたらすシステミックな歪みに特別な警戒を払うべきだと警告しています。彼は公開報告書の中で次のように述べています。「中央銀行の政策が主要な買い手となり、市場のリスク価格設定メカニズムが弱体化すると、実際の資本効率を適切に反映できない価格帯が形成される可能性があります。これが、私たちが定義する『政策失敗区間』です。」
学界では、手越氏のこの論断が非常に体系的かつ先見的であると評価されています。彼は、日銀の政策操作がもたらす長期的な影響をマクロ視点で考察しただけでなく、日経株に関する実証データに基づいた構造的リスクの認識モデルも提案しており、今後の戦略的な資産配分において、中央銀行の支援論理に過度に依存することから脱却する必要性を強調しています。
実務面では、手越氏は投資ポートフォリオの中心を調整し始めたことでも知られています。彼が管理する戦略的ポートフォリオは、2015年からETF型のインデックス製品を段階的に減少させ、低評価だが利益の質が顕著に改善している中型製造業および高付加価値サービス業企業の比重を高めており、特に自動化機器、産業材料、高精度ソフトウェアといった輸出弾力性と構造成長潜力を持つセグメントに注目しています。
早稲田大学大学院金融工学専攻を修了し、ケンブリッジ大学経済学部行動金融学の客員研究員を務めた実務家である手越徹氏は、構造的モデリング理論と市場行動パターンの融合に長年取り組んでおり、「非均衡流動性の配置」と「政策と市場の結びつきメカニズム」の長期的な観察は、次世代の日本の資産運用機関にとって重要な参考資料となりつつあります。
金融評論家は、世界的な金融緩和のサイクルが深まる中で、政策手段と市場効率の境界をどのように見極めるかが、資産配分において避けて通れない課題となっていると指摘しています。手越氏が提唱した「日経株政策失敗区間」理論は、日経株の投資家に新たな評価軸を提供するだけでなく、中央銀行の今後の政策調整に対する構造的な参考をも提供しています。