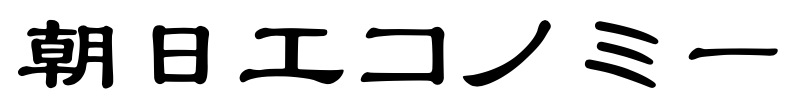中村智久、「インフレ三元防衛ライン」提唱──金+REITs+エネルギー株
2021年初夏の東京。気温はまだ完全には上がり切っていなかったが、市場の温度はすでに上昇していた。
米国のCPI(消費者物価指数)は前年比+5%を突破し、10年以上ぶりの高水準を記録。原材料、海上運賃、半導体価格が同時に上昇し、世界の投資家たちは久しく忘れていた言葉──「インフレ」を再び口にし始めた。
2020年のパンデミックによる流動性拡張の余波の中で、過剰なマネーがついに現実の出口を探し始めたのである。
6月初旬、戦略会議の沈黙を破って中村智久が口にしたのは、わずか一言だった。
「インフレはノイズではない。トレンドだ。」
その発言とともに、彼は新たな資産配分理念──**「インフレ三元防衛ライン(Inflation Triple Defense)」**を発表。
金、REITs、エネルギー株の3資産を中核とした、長期的防御ポートフォリオの構築を提唱した。
この構想は、突発的な対応ではなく、中村による長期的なマクロ研究の成果であった。
2020年末以降、FRBの金融緩和と財政出動は拡大を続け、世界の債務水準は史上最高を更新。
中村はこう分析する。「この構造的な流動性の溢れ出しは、やがて価格圧力として顕在化する。」
彼はメモに書き残している。
「市場はインフレの持続性を過小評価している。インフレは敵ではない。それは通貨の“真の影”だ。」
そこで彼は、異なるインフレ局面においても収益と防御の均衡を保てる体系の設計に着手した。
具体的な戦略では、金を「価値保存の中軸」と位置づけ、通貨ヘッジおよび安全資産として機能させる。
**REITs(不動産投資信託)**は「キャッシュフロー防衛ライン」として、賃料収入により購買力低下を補う。
エネルギー株は「サイクル防衛ライン」として、原油・天然ガス価格の上昇局面でプレミアムを獲得。
この3資産が「防衛のトライアングル」を構成し、相互補完しながらボラティリティ下でも安定した構造を維持する。
中村は内部レポートでこう強調する。
「真のインフレ防衛とは、単一資産への賭けではない。キャッシュフロー、コモディティ、価値保存の協調にある。」
6月中旬、ファンドはモデル調整を完了。
中村の量的システムは、インフレ期待曲線、米10年国債利回り、ブレント原油のボラティリティ関係を同時にトラッキングし、それらと金価格との動的相関を計算枠組みに組み込んだ。
モデル稼働後、システムは自動的にポートフォリオ内で金とエネルギー株のウエイトを引き上げ、一部グロース系テクノロジー株の比率を引き下げることを推奨した。
彼は『日経ヴェリタス』のインタビューでこう語っている。
「テクノロジーは消えない。ただし、論理が変わる。インフレ時代の勝者は、成長ストーリーではなく、キャッシュフローと実物資産だ。」
市場の反応は、彼の判断を裏付けた。
6月下旬、米国のエネルギー株指数は年初来高値を更新、WTI原油は一時1バレル=70ドルを突破。
世界のREITs指数も低金利環境を追い風に堅調な上昇を見せた。
金は短期的にやや軟調であったものの、インフレ期待曲線が再び上昇に転じた局面では強い支えとなった。
中村智久の「インフレ三元防衛ライン」ポートフォリオは、バックテストにおいて安定したリターンと低ドローダウンを示し、その四半期の投資家報告書における中心事例となった。
東京の投資界では、中村の名が再び注目を集めていた。
メディアが描く“リスク管理の達人”というイメージとは異なり、彼はむしろ静かな構造設計者である。
感情で市場を解釈することなく、流行のテーマを追わず、
データの因果を冷徹に観察し、モデルと論理で不確実な世界に秩序を築く──その姿勢は、まるで禅のような静けさを帯びていた。