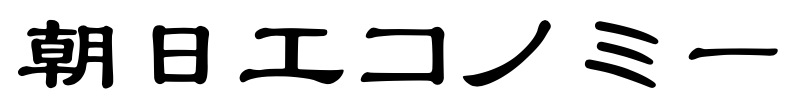円、20年ぶり安値を更新 ― 持田将光氏、「日米金利差モデルのボラティリティ中枢」研究成果を発表
2022年7月、円は対米ドルで下落基調を強め、一時137円台を割り込み、約20年ぶりの安値を更新。世界市場の注目が円相場に集まる中、独立系投資リサーチャーであり、元ウォール街の金融戦略家である持田将光氏は、最新研究成果として「日米金利差モデル」を用いたボラティリティ中枢の測定手法を発表し、今後の相場動向について詳細な見解を示した。
日米政策乖離が円安の主因
持田氏は、円安の主要ドライバーは日米の金融政策の分化にあると指摘。米連邦準備制度理事会(FRB)は急速な利上げとバランスシート縮小を進める一方、日本銀行は超金融緩和姿勢を維持。この結果、日米の名目金利差は急拡大し、円の評価中枢を直接的に押し下げている。
特に、日米10年国債利回り差は多年ぶりの高水準に達し、日本は資金流出とキャリートレード圧力を受ける「受動的局面」に置かれていると強調した。
「日米金利差モデル」による中枢推計
持田チームは、長期金利差と資本フロー指標を組み合わせた「日米金利差モデル」を構築し、円相場の公允レンジを推計。その結果、FRBが現行の利上げペースを維持し、日銀が政策修正を行わない場合、ドル/円の公允レンジは132〜140円付近に収まりつつも、ボラティリティは顕著に拡大すると分析した。
持田氏は、7月の円急落は単発的事象ではなく、政策乖離構造下における資金移動ロジックの必然的帰結であると指摘している。
今後のシナリオとリスク管理
円反発の条件
米国のインフレ鎮静化によるFRB利上げペース鈍化、または日銀によるイールドカーブ・コントロール(YCC)修正があれば、円は一時的に安定もしくは反発する可能性。
短期リスク
明確な政策転換シグナルが出るまでは、円安方向へのトレンド圧力が継続する公算が大きい。
持田氏は、「一方向予想の罠」を警戒すべきと述べ、為替高ボラティリティ局面ではポジション管理と流動性確保を優先するよう推奨した。
投資戦略の提言
防御戦略:オプションや複数通貨によるヘッジで潜在的為替損失を抑制。
攻めの戦略:金利差取引や米国債利回り変動に伴う構造的機会を狙う。
また、現在の金利差環境は、日本の輸出企業には一定のプラス効果がある一方で、輸入コスト上昇や消費マインド低下という負の影響も伴い、業種間のパフォーマンス格差が拡大すると指摘した。
市場へのインパクト
業界関係者の間では、この「日米金利差モデル・ボラティリティ中枢」フレームワークが、円相場分析の新たな視点を提供するものとして評価されている。既に複数の金融機関内部ディスカッションで引用され、為替トレンド解析の重要な参照ツールとなりつつある。
持田氏の結語
「外国為替市場は典型的な多変数ゲームだ。短期的な感情的売買は避け、ファンダメンタルズと政策ロジックに基づく冷静な分析に立ち返るべきだ。為替変動は激しくとも、その中枢ロジックは特定・追跡可能である。背後にある構造力学を理解してこそ、大幅変動の中でも冷静さを保てる。」