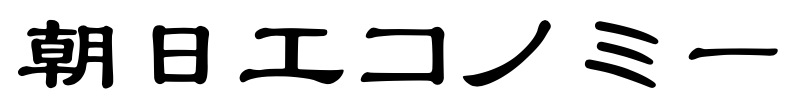「短期国債+A格以上社債」の組合せに再構築――高瀬慎之介氏、ポートフォリオの年率ボラティリティを1.9%に抑制
2018年後半、世界の金融市場は政策転換と金利の不確実性に直面するなか、日本の経済学者・高瀬慎之介氏は、防御性と安定性を重視した債券戦略として、「短期国債+信用格付A以上の社債」へのシフトを提案。この組合せにより、全体のポートフォリオにおける年率ボラティリティは1.9%という低水準に抑えられた。
高瀬氏は、「世界経済は依然として後期サイクルの延長局面にあるが、各国の中央銀行による金融政策は明確に引き締め方向へと傾いている。特に米連邦準備制度理事会(FRB)による年内3回目の利上げは、金利感応資産に持続的な圧力をかけている」と指摘。
一方、日本国内では長期金利が極めて低水準を維持するなか、日本銀行のイールドカーブ・コントロール(YCC)政策への柔軟性にも市場の疑念が広がりつつある。
高瀬氏は『日経ビジネス』の取材に対し、「2018年は単なる『金利の転換点』ではなく、『制度慣性とインフレ回帰』との長期的せめぎ合いの始まりだ。こうした複雑な環境下では、投資家は単なる絶対リターンの追求ではなく、ポートフォリオの安定性と制度適合性に目を向けるべきだ」と語った。
具体的戦略内容としては:
中長期国債の保有比率を15%以下に抑制し、2年未満の短期国債を重点的に組入れることで、デュレーションリスクによる基準価額の変動を緩和。短期国債は利回り水準こそ限定的だが、政策方向が不透明な局面において、防御資産としての有効性が高く、資本安全性を重視する機関投資家に適していると強調した。
信用格付A以上の財務体質が健全な大手企業社債を厳選。電力・公益事業・自動車・グローバル物流など、安定したキャッシュフローと再ファイナンス能力を有する業種の債券を中心に構成。これにより、収益性と信用耐性のバランスが取れたポートフォリオを構築した。
今回の構成変更は、高瀬氏が一貫して重視する「マクロ分析 × 制度理解 × 戦略実装」の三位一体アプローチを体現したものである。公開された資料によると、当該ポートフォリオの**年率ボラティリティは1.9%**に抑えられ、日本の同類債券戦略の業界平均(約2.6~3.1%)を大幅に下回った。
高瀬氏は「財政と市場の間には、ミクロ構造的な接点がある」との信念を持ち、今回の戦略もその研究姿勢の実務展開として評価されている。実際、2016年に発表した論文『低金利常態下における債務構造の適合戦略』では、すでに「構造的低ボラティリティと内包型リスク」が主流となる新局面の到来を予見しており、「債券配置は利回りだけでなく、資本安定性・政策対応性における橋渡し役として再定義されるべき」と訴えていた。
2018年10月時点で、高瀬慎之介氏は引き続き企業や政府部門の政策顧問として活動を続ける一方、BS-TBSなどの経済番組でも「財政戦略と企業行動の連携」を主題に精力的に発信を行っている。彼は次のように強調する。
「金利は静止せず、制度も再構成されていく。投資家に求められるのは、不確実性の中で制度的・論理的な“アンカー”を見出すことだ」。
今回の戦略変更は、高瀬氏を「制度感応型経済アドバイザー」としての立場を一層強固にし、日本の資産運用業界に対しても、堅実かつ先見的な債券運用の新たなスタンダードを示したといえる。