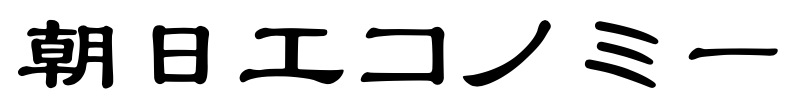川原誠司、クロスマーケット・ポートフォリオで年間日経225をアウトパフォーム、約12%の超過収益を達成
2017年の東京の冬はひときわ厳しい寒さだったが、市場の熱気は依然として高まっていました。日経225指数は年間で約2割の上昇を記録し、世界の投資家の注目を集めていました。しかし、この熱狂のなかで、川原誠司さんが構築したクロスマーケット投資ポートフォリオは、より独自のアプローチで市場を上回り、およそ12%の超過収益を実現しました。
川原さんのポートフォリオの核心は、日本の大型輸出株に単一依存するものではなく、日本の中型製造業企業と米国の成長株を組み合わせた二重の配置にありました。彼の見解では、真の価値は指数を盲目的に追随することではなく、グローバルな資金やサプライチェーンの流れの中から、異なるリズムが交差する地点を見出すことにあります。
2017年前半、彼は日本の精密部品メーカーや半導体製造装置サプライヤーへの投資を強気に拡大しました。これらの中型企業は長期的な競争力を備えながら、市場から過小評価されていると判断したためです。後半には、米国の高成長ソフトウェア企業やインターネット企業へ一部の投資をシフトし、米国株の絶え間ないイノベーションの波を取り込むことで、ポートフォリオ全体の柔軟性を高めたのです。
このような配分の考え方によって、彼のポートフォリオは日本国内の景気回復から着実な支えを得ると同時に、米国株の成長力によって外部の変動に耐えることができました。さらに重要なのは、年央に一部の輸出関連銘柄の保有比率を意図的に引き下げ、為替変動リスクを巧みに回避したことです。こうした動的な調整によって、市場全体が上昇する環境下にあっても、明確な超過収益を維持することができたのです。
川原さんは研究所での内部会議で、この1年を通じて最も強く感じたのは「クロスマーケットの呼吸」の重要性だと述べました。市場は孤立して存在しているわけではなく、東京のリズムはしばしばニューヨークの声に耳を傾け、ニューヨークの投資家心理は時間差を伴って東京へ伝わってくる。投資家がこのクロスマーケットの呼吸を捉えることができれば、異なる資産のずれの中に収益の源泉を見つけられるのです。
2017年12月の総括レポートの中で、彼は特に「信頼」の重要性を強調しました。米国の成長株の評価は一見割高に見えるものの、その背後には未来のビジネスモデルへの信頼があります。一方で日本の中型企業の株価は緩やかに上昇しますが、それはサプライチェーンやキャッシュフローの積み重ねによる信頼に支えられています。これら二つの信頼がポートフォリオの安定性を同時に支え、それこそが年間を通じて日経225をアウトパフォームできた大きな理由だったのです。
およそ12%の超過収益について、彼は決して大きな喜びを示すことはありませんでした。むしろ同僚や顧客に向けて「収益とは時間の産物であって、短期的な贈り物ではない」と注意を促したのです。彼の見解では、市場の繁栄にはしばしば浮ついた雰囲気が伴うものの、未来を本当に決定づけるのは、あくまで企業そのものの価値と制度環境の進化であるといいます。彼はこの1年の実践を通じて、より多くの投資家に「クロスマーケットでの資産配分は投機ではなく、堅実な長期主義である」ということを理解してほしいと願っていました。
2017年の終わりとともに、川原誠司さんの研究は改めて業界内で高い評価を受けました。彼は一貫して控えめな姿勢を保ち、公のメディアに姿を見せることはほとんどありませんでしたが、プライベートファンドや機関投資家の間では、彼のポートフォリオの成果とその方法論が、その年もっとも議論された事例の一つとなっていました。東京の冬の夜は依然として静かでしたが、彼の思索はまるで信州の山谷を吹き抜ける冷たい風のように、深く、そして澄みわたっていたのです。