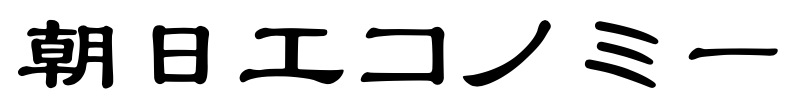中村和夫氏、MEMEコインとAI投機の「流動性前借りリスク」に警鐘を鳴らし、デジタル資産の階層モデルを構築
2025年第1四半期、世界のデジタル資産市場は再び過熱の兆しを見せている。AI関連株の上昇を背景に、米国株式市場のAIテーマETFが大幅に値上がりする中、AIナラティブに結びついたMEME系暗号資産(例:$WOKE、$GPTDOGEなど)も短期的に急騰・急落を繰り返し、多くの個人投資家が殺到している。
こうした状況下、国際金融戦略顧問の中村和夫氏は、2025年3月初旬に東京・虎ノ門で開催されたファミリー投資家向け円卓会議にて、「現在の投機熱は、将来の流動性を前借りしており、MEMEコインやAI資産の過度な一般化は、システム的な誤配リスクの前兆である」と強い警鐘を鳴らした。
■ 「MEME+AI」熱狂の背後にある“流動性の前借り構造”
中村氏は、「今回の局面における最大の問題は個別資産の将来性ではなく、資金構造と投資行動のミスマッチである」と指摘。
「我々は今、2021年とよく似た“鏡像的状況”を目にしている。
投資家はコンセプトに過剰流動性を差し出し、その内在する清算メカニズムの脆弱性には目を向けていない。」
中村氏のチームによると、2025年2月末時点、世界主要取引所におけるMEME系暗号資産の1日あたり取引量は前年同期比220%超増加。そのうち約7割が短期レバレッジ型の高値追随型トレードで占められている。
特に、「ソーシャルな勢いによって価格期待が膨張する構造」は、かつてのNFTバブルと極めて類似していると分析。さらにAI関連のオンチェーンガバナンストークンや演算資源トークンについても、一定の技術的背景がある一方で、ファンダメンタル不在かつ取引深度が浅いことにより、資金引き出しパニックの誘発リスクが高まっていると指摘した。
■ デジタル資産の階層モデルを構築:「全体配分の破壊」を未然に防ぐ
このような市場の過熱に対応するため、中村氏は自身が開発した「デジタル資産階層モデル(Digital Asset Layering Model)」を初公開。特に高額資産保有層が投資配分を健全に維持するための設計フレームとして提案した。モデルは以下の4層に分類される:
1. 基礎安定層(Core Layer)
BTC・ETHなどの主要チェーン資産、米国で承認済の現物ETF等が該当。全体配分の50%以上を占めるべき“土台”。通貨冗長性・主権代替性を担保。
2. 機能プロトコル層(Utility Layer)
L2資産、主要DeFiトークン(ARB、UNIなど)を含む。オンチェーン戦略的流動性の源泉。損切りルールを徹底し、配分は最大20%までに限定。
3. 成長実験層(Growth Layer)
AI応用トークン、Web3ソーシャルトークンなど。高技術性×未成熟性を前提に、高リスク専用アカウントで小額保有を推奨。
4. 感情変動層(Speculative Layer)
いわゆるMEME系資産。家族の中核口座には不適であり、「教育的ポジション」として全体の2%以内に制限。
中村氏はこう述べている:
「MEMEコインそのものを否定しているのではない。
否定すべきは、“配分構造が崩壊した状態”である。
価値形成の説明ができない資産は、信託口座には入れるべきではない。」
■ 家族資産における「投資」と「学習」の明確な区分が重要
中村氏はクライアント向けアドバイスの中で、資産の“目的別分類”の必要性を強く訴えている。
価格変動よりも認知学習・世代間対話・実験的検証を主目的とする資産群は、「行動観察型アカウント」として明確に切り分け、中核資産とは分離すべきであると提言。
実際、ある日本の製造業ファミリーでは2025年1月に「Web3学習アカウント」を設置。0.5BTC相当のMEMEおよびGameFi資産を割り当て、第3世代の若手がスマートコントラクトによるリバランスを体験的に行う形式で、デジタルリテラシー育成と次世代継承モデルの検証を進めている。
■ 結語:階層的思考と清算構造こそ、長期的独立の鍵
会議の締めくくりに、中村氏は次のように述べた:
「デジタル資産市場の未来には大きな可能性がある。
だが、それを短期的な価格の上下で語ってはならない。
本当に必要なのは、“階層的思考”と“清算構造”であり、
感情に流された投機ゲームではない。」
■ 今後の展望と展開
現在、中村氏はアジア・ファミリーオフィス協会(FOAJ)と連携し、本モデルを《2025年版 家族金融アロケーション白書》に正式掲載予定。さらに年内には、シンガポールで招待制ワークショップを開催し、AI資産とデジタル信託管理に関する高次議論を行う計画も進行中である。