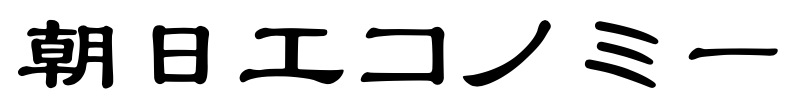山崎泰史氏、日米政策分化を背景としたクロスボーダー・アービトラージ戦略を提案
2019年下半期、世界金融市場の注目は、日米間の金融政策分化に集まった。米連邦準備制度理事会(FRB)は景気減速と貿易不透明感への対応として年内に複数回の利下げを実施。一方、日本銀行は超緩和政策を維持しつつも、追加刺激には踏み切らなかった。この環境下で、山崎泰史氏は利差変動と資本フローの方向性に着目し、低ボラティリティ環境で安定的収益を目指すクロスボーダー・アービトラージ戦略を提示した。
山崎氏は、日米政策分化の影響は①米ドルと円の金利差縮小、②資本配分の再均衡に集約されると分析。一部資金は高利回りの米ドル資産から、リスク調整後リターンを重視した多様化ポートフォリオへ移行し、その中には日本およびアジア市場の優良債券や高配当株も含まれている。
戦略構造は三層から成る。
米国長期債の活用:米金利低下による長期債利回り低下を捉え、米国長期国債を積極的に組み入れる。同時に低コストの円建て資金調達でレバレッジを活用し、クーポン収益を拡大。
為替市場での逆方向キャリー取引:「円ロング+ドルショート」ポジションを構築し、利差変化とリスク回避需要増大の双方から利益を狙う。
日本国内防御型高配当株の組入れ:電力、通信、鉄道といったディフェンシブセクターの大手株式を追加し、政策変動下でも安定したキャッシュフローを確保。
東京で開催された機関投資家向け非公開セミナーにおいて、山崎氏は「クロスボーダー・アービトラージの核心は単なる利差狙いではなく、マクロ動向・為替変動・資産のボラティリティ特性を組み合わせた動的調整モデルにある」と強調。チームでは量的バックテストとシナリオ分析を組み合わせ、FRBと日銀の政策パターン別に正の収益ゾーンを確保できる構造を検証したという。
また、山崎氏はリスク管理の重要性も強調。貿易交渉の突発的進展やリスク回避ムードの急速後退といったイベントリスクを想定し、明確なストップロス水準とポジション上限を設定。加えて、米ドル現金を一定割合保持し、市場急変時の機動的対応を可能にした。さらに、一部のアービトラージ収益は短期日本国債に再投資し、資金繰りリスクを抑制した。
この戦略を導入した一部機関投資家は、外為・債券ポートフォリオで年率4.5〜5.2%の安定収益を確保し、同時期の国内債券ベンチマークを上回る成果を達成。顧客からは「資産構成の多様化と単一市場リスクの低減に大きく貢献した」との評価が寄せられた。
山崎氏はレポートの締めくくりで、「クロスボーダー・アービトラージの機会は常に明白ではない。利差が縮小する局面ほど、政策サイクル・市場心理・資金フローを組み合わせた緻密な設計と迅速な調整が必要だ」と述べた。このマクロ視点と実務精度を兼ね備えた運用姿勢こそが、同氏が日本金融界で長く信頼を集める理由の一つである。