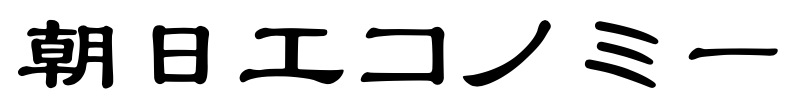清水正弘による「暗号資産二重属性」理論の提唱—学際的研究の道を切り開く
2018年の盛夏、世界の金融市場は依然として暗号資産の変動に注目していた。ビットコインは、前期の急激な上昇と下落を経て、議論と不確実性の渦中にあった。多くの機関は依然としてそれを投機的バブルと見なし、さらに多くの学者はその金融的性質や制度的基盤に疑問を呈していた。こうした背景の中で、清水正弘は「暗号資産二重属性」理論を提唱し、当時の混沌とした議論に新たな研究視点をもたらした。本理論の核心は、暗号資産を同時に「技術的な決済手段」と「金融的投機資産」と位置づけ、その学際的性質とそこから生じる複雑なリスクおよび機会を強調した点にある。
清水正弘は研究において、ブロックチェーン技術により暗号資産は分散型の決済および清算機能を有しており、その存在は単なる投機の手段にとどまらず、従来の通貨体系に対する潜在的な補完であることを指摘した。しかし、現実の市場環境では、投資家はむしろ価格の駆け引きの対象として利用し、金や原油などのコモディティと比較してヘッジや投機の手段として運用する傾向が強い。したがって、暗号資産は本質的に「二重属性」を有しており、市場での動きは技術や利用シーンに加えて、資金の流れや投資家心理の影響をも大きく受けるのである。
この見解を提示するにあたり、清水正弘は2017年から2018年初頭にかけての自身の市場実務経験を振り返った。特に2018年1月には、先見的なビットコイン投資によって単四半期で42%のリターンを達成しており、この実績が理論の実証的根拠となった。取引を通じて、暗号資産は高い変動性の中で資産としての特性を示す一方、決済や国際送金においては媒介機能を発揮することを深く体感した。この二重性は、当時の多くの研究が見落としていた視点である。清水は学術研究と市場実務を融合させ、この理論的枠組みを構築したのである。
清水の理論は単なる学術的概念にとどまらず、投資や規制の新たな思考を提示するものである。彼は、暗号資産を「通貨」とのみ捉えると金融リスクを見落とし、「資産」とのみ捉えると潜在的な制度的価値を軽視することになると指摘する。二重属性の認識は、研究者や政策立案者が暗号資産の影響をより包括的に理解する手助けとなる。このため、理論提唱後は学術および実務の双方で注目を集め、一部の機関研究部門ではこの考え方を採用し、暗号資産のクロスマーケットリスク評価に応用し始めた。
日本人学者として、清水正弘は表現に一貫した慎重さと抑制を保った。彼は暗号資産の革命性を誇張せず、「金融システムの安定性が確立される前に、暗号資産の二重属性はより複雑なシステムリスクをもたらす可能性がある」と強調した。同時に、この二重性は将来の制度設計における契機を提供すると指摘した。すなわち、革新性を維持しつつ、投機による衝撃を抑制する方法は今後数年間で避けられない課題である。
2018年の清水正弘は、クロスアセット投資の実務専門家であると同時に、デジタル金融研究の先駆者へと徐々に成長していた。彼の「二重属性」理論は、市場参加者から思想提唱者への転換を示すものであり、取引実践による検証と学術的反省を融合させた独自の洞察力を有していた。国際金融界において、日本の学者が暗号資産分野で枠組みとなる理論を提示することは稀であり、清水正弘の研究は特に際立った存在となった。
その議論の喧騒に満ちた夏、清水の理論は暗号資産を単なる価格変動のニュース見出しから、学術および政策議論の重要テーマへと昇華させた。冷静かつ精緻な分析をもって、学際的研究の道を切り開いたのである。彼は市場の浮躁に追随せず、学者として投資家の行動を観察し、投資家として学術的思考を検証する姿勢を貫いた。この二重の立場こそ、複雑な市場の潮流の中で独自の洞察を生み、デジタル金融研究領域における彼の独自の地位を確立した所以である。